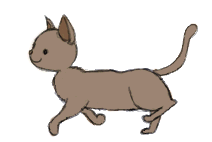日本理学整体学会公認

Therapeutic Manipulation without Pain
ロコモと整体(3)
本シリーズでロコモティブ・シンドロームを紹介するにあたって、メタボリック・シンドロームと対比する形で進めてきました。 もう一度復習しておきましょう。
| メタボリック・シンドローム | ロコモティブ・シンドローム | |
|---|---|---|
| 日本語 | 代謝異常症候群 | 運動器症候群 |
| 定義 | 動脈硬化の予備軍 | 運動器不安定症の予備軍 |
| 診断基準 | 腹囲が基準値以上で高血圧・高脂血症・高血糖のうち2つ以上の症状が認められる | ロコチェックで該当項目が1つ以上あった上で専門医が判定 |
平たく言うとメタボは内臓系の異常、ロコモは運動器の異常ということになり、一見無関係のように見えますが、実はこれらは大きく関係しているのです。
一番分かりやすい例を示すと、お腹が痛いときを想像してみてください。
お腹を抱えて背を丸めますよね。
背すじを伸ばせと言われても、本当にお腹が痛いときは冷や汗たらたら顔面蒼白、足はガクガクとなってきます。
このように内臓に異常があると、身体の形や動きに現れてきます。
逆もまた真なりです。
身体の形に異常があると運動器に障害が発生することは前回述べましたが、悪影響があるのは運動器だけではなく、神経や内臓にも及びます。
内臓にまで及ぶというのは、内臓の働きをコントロールしているのは自律神経であり、これが圧迫されて正しく機能しないと内臓が正常に働かなくなるからです。
また、例えば身体の筋肉が常に緊張状態にあり呼吸が浅くなると高血圧につながりますし、猫背の姿勢は首や頭のまわりの筋肉を緊張させ頭痛の原因になります。
これまで何度も述べているように身体の形や動きを作っているのは筋肉です。
筋肉の働きを正常化することで正しい姿勢が維持され、そのことにより運動器だけでなく血管・神経も正しく働くことができるようになります。
神経には運動神経・感覚神経・自律神経がありますので、自律神経にコントロールされている内臓の働きも正常になります。
以上、6回に亘りロコモティブ・シンドロームについて述べてきました。
メタボの人はロコモの予備軍であり、ロコモの人はメタボを含む様々な内臓疾患の予備軍となり得るといことが伝えられたでしょうか。
そして、整体で身体の形を整えることが、これらの解決の手段の一つになるということが分かっていただけたでしょうか。
拙い文章表現で言いたいことの半分も書けたかなという不十分な思いがありますが、皆さんが少しでもご自分の身体の形や動きに興味をもっていただければ幸いです。